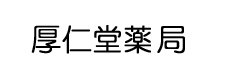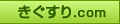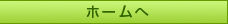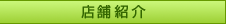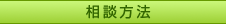治療例集 №3 慢性気管支喘息 鹿児島 漢方専門厚仁堂薬局
★53才、男性。身長160cm、体重50kg
【主訴】
慢性気管支喘息。30才頃から発症。仕事で微粉末を吸い込む機会が増え、そのためかここ2~3年特に悪く、喘息発作が続いている。
発作性の呼吸困難、喘鳴(ヒューヒュー)、咳嗽、鼻水(サラサラ)を伴い、痰(サラサラ~白粘、および黄粘)が喀出されると楽になる、発作時には汗を伴う(ベトベトした感じ)。
【病歴】
肺門リンパの腫れ
蓄膿症
【併用薬】
以前は小青竜湯が有効だったが、今では無効。
【全身症状】
寒熱:四肢冷(+)
二便:大便1日1回
小便1日5~6回
食欲:普通
飲水:普通
全身:とても疲れやすい
浮腫:ない
面色:青白い
舌:舌苔微白、舌質淡。
<漢方的病理分析>
慢性気管支喘息は「標実本虚」という構造を持つことが多い。「標実本虚」とは、根本的な原因は体のある部分の虚弱さ(本虚)にあるものの、実際に表面上出ている症状は毒素症状(標実)をあらわす、という2重構造を持つ病変をいう。アレルギー症状に多く見られる。今回の場合もこの標実本虚に該当すると思われる。根本的原因(本虚)は、非常に疲れやすいことから「元気の不足」があると思われる。一方、喘鳴を伴う喘息・痰(サラサラ~白粘)・鼻水(サラサラ)の状態から「肺の冷え」、痰(黄色)・発作時の汗(ベトベト)から「肺の熱」、というの二つの表面上の毒素(標実)が考えられる。
<漢方的治療方針>
第一に喘息発作を抑えることを目標に「肺の冷え」および「肺の熱」を治療し、喘息症状が治まった後、喘息が出ない体作りを目標に「元気の不足」を治療する。
<実際に使った漢方処方>
「肺の冷えおよび肺の熱」:小青竜湯合麻杏甘石湯
「元気補不足を補う」:補中益気湯
<結果>
まず、小青竜湯合麻杏甘石湯を投与(標実の治療)。服用3日にして喘息発作でなくなる。
この後も同処方を続け喘息発作のでない状態を5ヶ月ほど続ける。
その後、根本治療として補中益気湯を投与(本虚の治療)。1年ほど服用を続け良好。その後は、季節の変わり目に発作が出そうになる時は小青竜湯号麻杏甘石湯でやり過ごし、平素は補中益気湯服用で安定した状態を保っている。
<考察>
喘息治療は上記のごとく「今ある喘息発作をコントロールする薬」と「喘息発作の起らない体質作りをする薬」との2段構えの治療が必要である。このあたりを構造的に理解しないとなかなかうまくはゆかない。また、肺に「冷え」と「熱」という相反する病変があることは一見矛盾するようであるが、実際には気管支喘息においてよく見られる現象である。
発作を止めるだけであればステロイド吸入剤は非常に有効である。ところが、ステロイド吸入剤は「今おこっている発作を止めること」は出来ても「発作の起らない体作り」はできない。漢方薬にはそれができる。ここに漢方薬の臨床的価値があると思う。
|
更新日: 2011/03/24 |
|
治療例集 №2扁桃腺を腫らしやすい 鹿児島 漢方専門厚仁堂薬局
★44歳、男性。身長170cm、体重58kg 【主訴】 一年中カゼをひいている。カゼを引くとすぐ扁桃腺がはれ40度の高熱を出し、咽痛・倦怠がひどい。病院で抗生物質と解熱剤を服用して治す、またしばらくしたら発熱、を繰り返している。同時に蓄膿症を持っていて常に黄色鼻水がある。また扁桃腺が腫れると黄色い痰を伴う咳が出る。 【病歴】 肺炎(カゼをこじらせて) 十二指腸潰瘍(24歳時、内服にて治療) 【併用薬】 カゼ薬、抗生物質 【全身症状】 寒熱:冷え性(-) 二便:大便:1日1回 小便:1日6~7回 食欲:普通 全身:疲れやすい。 皮膚:乾燥、浅黒い。学生の頃は化膿性ニキビが多発 <漢方的病理分析> 典型的な「解毒症体質」と思われる。「解毒症体質」とは「肝臓で解毒を必要とする毒素を有する体質」と定義され、「外界の刺激に容易に反応し易い体質」とも解釈されている。具体的にはその代表に「結核菌に犯されやすい体質」がある。今日においては幼年期・青年期には慢性中耳炎、慢性蓄膿症、慢性扁桃腺炎、アデノイド、化膿性ニキビなど、壮年期以降は肝臓・腎臓・すい臓・前立腺・卵巣・子宮・膀胱・肛門などの慢性炎症がこれに該当する。解毒症体質はそのほかにも長身・痩せ型・皮膚浅黒い・くすぐったがり、といった傾向がある。今回の場合はこの「解毒症体質」に加えて、疲れやすいことから「気虚(体力の不足)」、化膿性の痰を伴う咳から「肺熱(肺に熱がこもった状態)」を兼ねているものと思われる。 <漢方的治療方針> 「解毒症体質」に対しては解毒を、「気虚」には元気を補い、「肺熱」には肺の熱を冷ます、などの治療を行う。 <実際に用いた漢方処方> 荊芥連翹湯(解毒症体質)+補中益気湯(気虚)+麻杏甘石湯(肺熱) <結果> 服用をはじめてから最初に変化があったのは蓄膿症の改善であった(黄色の鼻水の激減)。 その後、暫時発熱・咽痛の頻度が減少。ただ、発熱時は漢方薬だけでは追いつかずに病院の抗生物質・解熱薬をたびたび併用した。またのどの腫れ痛み・鼻水の状態によっては荊芥連翹湯+桔梗石膏+補中益気湯あるいは荊芥連翹湯+排膿散及湯+補中益気湯などとして適宜乗り越えてきた。最終的には荊芥連翹湯+排膿散及湯+補中益気湯で最も安定した効果を発揮。その後紆余曲折あったものの、カゼを引かない状態を1年間確認の後に暫減、廃薬。 <考察> 慢性扁桃腺炎は辛いものらしい。すでに発熱してしまったものには抗生物質・解熱薬が効果を発揮するが、あくまで「発熱してからの対処療法」にすぎず「扁桃腺が腫れない体質作り」はできない。ところが、漢方薬にはこの「扁桃腺が腫れない体質作り」ができる。ここに漢方薬の利用価値があると思う。慢性扁桃腺炎をそのまま放置すると40~50才以降になるとその毒が下半身へと伝わり腎臓・膀胱・前立腺の慢性炎症を引き起こす恐れがあるので注意が必要である。 |
|
更新日: 2011/03/10 |
|
治療例集 №1不妊 鹿児島 漢方専門厚仁堂薬局
★29歳、女性。身長164cm、体重53kg 【主訴】 不妊。結婚3年になるが妊娠しない。病院の診断では右卵巣が腫れているとのことで右下腹部の引きつれる痛みが常にあり、また子宮内膜症もあるとのこと。病院でホルモン療法をすすめられたが、ホルモン療法に抵抗を感じ、漢方治療を希望して来局。 基礎体温表は2層に分かれるものの排卵後高温期への移行に日数(4日ほど)がかかり、その結果高温期が短い。また、高温期の上がり自体も弱い。 【現病・病歴】 胃下垂 膀胱炎を起こしやすい。 【併用薬】 エスタックイブ(月経痛) 【全身症状】 手足:冷え性 二便:大便2~3日に1回 小便1日10回(無色透明) 【全身】 疲れやすい。特に朝が弱い。 【食欲】 少ない。 【月経】 周期(29日)、経期(7日間)、月経痛(開始1日前から痛みはじめる。下腹部~腰。激痛⇒エスタックイブ使用)、経血は暗赤色でレバー様の塊を多く交える。 【舌】 舌質:淡・胖 舌苔:白 【血圧】 上(100前後)、下(60前後) <漢方的病理分析> 右下腹部の痛み・子宮内膜症・月経の状態から「血瘀(けつお・流れの悪くなった悪い血・古血)」 疲れやすさ・胃下垂・舌の状態・低血圧から「気虚(ききょ・体力の不足した状態)」 冷え性・高温期の未発達から「陽虚(ようきょ・体の冷えた状態)」 これら三つが複雑に絡み合い不妊の原因となっていると思われる。 <漢方的治療方針> 血瘀(悪い血・古血)を取り除き、「気虚」を補い、「陽虚」を温める。 <実際に使用した漢方処方> 芎帰調血飲第一加減+補中益気湯+五積散 <結果> X年 10/11:服用開始 11/11:月経痛(↓↓)、下肢冷(↓)、食欲・元気(↑) ~以後上記処方を継続服用~ X+1年 6月:妊娠確認。来年3月出産予定。安胎のため漢方薬を上記処方から当帰芍薬散+補中益気湯+香蘇散に変更。 X+2年 3/15:普通分娩にて出産。男児・2300g。その後、出産時の血瘀を残さないために芎帰調血飲第一加減を100日間服用。 <考察> 治療開始から妊娠にいたるまで8ヶ月弱という比較的長い時間を要した例である。子宮内膜症という器質的病変がある場合はどうしても時間がかかるようである。 今回のような「血瘀」、「気虚」、「陽虚」といった病変はいずれも不妊に比較的多く見られるパターンである。このほかにも「腎虚」(初潮が遅い)、「ストレス型」(基礎体温表がジグザグ)、「無排卵型」など様々である。これらを正確に分析し、適切な漢方薬を選択することが大切である。 ホルモン治療になじめない方々は実際のところ多い。そのような方々の受け皿のひとつとして漢方薬は有効であると思う。 |
|
更新日: 2011/03/02 |