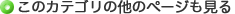きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
地図から学ぶ、生薬(きぐすり)のふるさと
ハスはハス科の多年生の水草です。水田や池、堀などに栽培され、細い細長い根茎は節が多く白く泥の中を這い、たまに分枝し、円柱形で、秋になるとその先端部は肥厚し、この肥厚した部分をレンコン(蓮根)と言います。
葉は地下茎から出て、葉柄は長く、水中から突き出す空中葉と水面に浮かぶ浮葉があります。葉柄は円柱形で表面には無数のトゲがあります。夏には花柄の先にピンク~紅色、白色の大形の花をつけます。

わが国では古事記に蓮(ハチス)花で出てきます。その頃から、葉は食べ物を盛るのに用 いられていました。この頃は仏との関係は出てきませんが、平安時代には仏教の経典の中にでてきます。
レンコンは西暦700年頃から食用とされ”ハチスの根”として記録があるようです。江戸時代には中国から唐蓮が花ハスとして入り観賞用に栽培されていたようです。インドではハスは”水・泥より生まれるもの”とされ、女性の生殖を象徴していたようで、蓮女神があります。ハスはまた浄土との結びつきが深くインド仏教ではハスは仏陀の誕生を告げて花を咲かせたとされています。さらに極楽の世界の中心には、青・赤・黄・白の光を放つ4種の蓮の華の蓮池があり、蓮の華で満ちた浄土が記されています。また中国では西方の浄土は神聖な蓮の池とされ、仏の聖なる植物と考えられ、日本でも境内に蓮の池を作るようになったようです。古代エジプトでも出てきます。昔から人と神仏を繋ぐ植物として扱われてきました。
蜂の巣に似たハスの果托
実の入っている穴と果托がアシナガバチの巣をひっくり返した形に似ていることから、ハスの別名が”ハチス(蜂巣)”と言われます。

最初は花の観賞用に中国から奈良時代に入ってきたと思われますが、鎌倉時代に食用のハスが入ってきました。明治以降に導入された中国種は地下茎が浅く、丸みがあり、病気に強いので、現在の栽培の主流になっています。それ以前のレンコンは地下茎が深く、スリムですが、肉質が軟らかいのが特徴です。
レンコンの穴

ハスの地下茎を切ると、普通は、真ん中に1個、周りに9個の穴が空いています。 その周りの穴のうち上(水面に近いほう)の2個は小さいですね。
このことから節がなくてもどちらの方が上か分かります。他に葉や葉柄にも穴が空いています。葉柄にもレンコンと同じような穴が有ります。
葉柄を切って、葉の中央に石けん水を少し入れ、切った葉柄から吹くと、シャボン玉が出来ますよ。試してみる価値あり!

これらの穴は連結していて通気孔になっていています。根に外の空気を送り込む入り口が葉の中央にあるのですね。

しかし、地下茎を泥水の中で折ると、穴に泥が入ります。穴の中は弱い減圧状態なのですね。
大賀ハス
日本では、有名なのが「大賀ハス」です。
2000年の眠りからさめたハスの実を、1951年に千葉県で大賀一良博士が見つけ、見事に花を咲かせました。
 |
 |
現在は全国に広がり市内の至る所で栽培され,熊本大学薬用植物園でも昨年花を咲かせました。綺麗ですね。花は朝音を立てて咲きます?日中は咲いていますが、夕方にすぼみ、4日で花びらが散ります。

- はじめに
- 日本の生薬(きぐすり)を学ぼう
- 忘れ去られた石菖[1]~石菖との出会い~
- 忘れ去られた石菖[2]~石菖って?~
- 忘れ去られた石菖[3]~石風呂の文化~
- 忘れ去られた石菖[4]~茶や花の文化の中へ~
- 忘れ去られた石菖[5]~聖なる場所~
- 「おきぐすりのふるさと」富山
- 小豆島のオリーブの魅力
- 種子島におけるガジュツの収穫
- 鞆(とも)の保命酒
- 熊本の川“緑川、白川、黒川”色々
- 日本に一つ日本一の味噌の天神
- ハスって、な~に?
- 熊本名産「からし蓮根」
- 薬用に用いる「ハス」
- 牧野富太郎
- 伊吹山の薬草[1] ~伊吹山にはなぜ薬草が多いのか?~
- 伊吹山の薬草[2] ~日本武尊は伊吹山の荒神にトリカブトで反撃されたか~
- 伊吹山の薬草[3] ~コンブリ~
- 伊吹山の薬草[4] ~甘茶~
- くすり屋の町 道修町
- 除虫菊
- 世界の生薬(きぐすり)を学ぼう
- 茯苓の産地を訪ねて~1~
- 茯苓の産地を訪ねて~2~
- ローズヒップに出逢う旅:チリ
- ベトナム桂皮